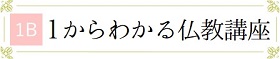周りの人を思いやり親切にすれば、必ず自分も大事にされる-「無財の七施」について

こんにちは。「1からわかる仏教講座」スタッフのkakoです。
仏教講座で学んだことをご紹介しています。
前回はお釈迦様がたくさんの善を6つにまとめられた「六度万行」について学びました。
前回の記事はこちら
今回は、六度万行の中から特に「布施」について、詳しく見ていきましょう。
お金や物がなくても実行できる「布施」とは?
「布施」とは「広く与える」という意味で、現代の言葉でいえば「親切」ということでしたね。
一般に、葬式や法事でお経を読んでもらったお礼のこととして使われていますが、それだけではなく、お世話になっている人や困っている人にお金をものや渡すことも布施なのです。
具体的には
- 義援金を出して、被災して苦しまれている方の、援助・応援をする
- 結婚記念日には、毎年奥さんに、思い出レストランで、お花をプレゼントする
- 職場の同僚に、旅行帰りには、地域限定のお菓子をお土産に買ってくる
などですね。
これらはとても喜ばれることであり、積極的にやっていきたいことなのですが、一方でお金や物に余裕がないと、なかなかできないものですね。
ところが仏教では、お金がなくても、物がなくても、心がけさえあれば周りの人たちに喜んでもらう「布施」があることを教えられています。
これを「無財の七施」と言い、『雑宝蔵経』というお経に以下の7つが説かれています。
- 眼施(げんせ)
- 和顔悦色施(わげんえっしょくせ)
- 言辞施(ごんじせ)
- 身施(しんせ)
- 心施(しんせ)
- 牀座施(しょうざせ)
- 房舎施(ぼうしゃせ)
七通りあるので七施と言われるのですね
この七つを1つ1つを具体例を通して、みなさんと学びたいと思います。
心がけがあれば実行でき、周りから大事にされる「無財の七施」
眼施(げんせ)
優しいあたたかい視線、まなざしで相手を見るということです。
「眼は口ほどに物をいう」と言われるように、眼ほど感情を映し出すものはありません。
初対面の人に良い印象もってもらうのに効果的なのは、気の利いた言葉よりも優しいまなざしを送ることです。
そうするとその相手のことを悪い人だとは、絶対に思わなくなるからです。
「なんとなくいい人だな」
「あの人がいると場が和む」
などと思ってもらえるでしょう。
反対に、口角をあげて本人は笑って接しているつもりでも、眼が笑っていないと、作り笑いと見透かされ、「不機嫌なのかな」「怖いな、近寄りがたいな」と思われてしまい、残念な結果になります。
なので、眼の笑顔は重要ですね。
和顔悦色施(わげんえっしょくせ)
「和顔」とは和やかな顔、「悦色」は喜びの表情ということで、笑顔のことです。
笑顔を向けられて嫌な人はないですね。明るくうれしい気持ちになります。
相手に対してだけでなく、医学的にも心理学的にも、笑顔が健康に与える好影響が実証されています。
笑顔は免疫力をアップさせ病気になりにくくなり、ストレス解消、軽い運動のような効果があるそうです。
最初は作り笑いでも、笑っているうちに本当に気分も和らぎ、上向きなってくるとも言われます。
言辞施(ごんじせ)
心からの優しい言葉をかけることです。
「大変でしたね」
「本当にうれしいです」
「感謝でいっぱいです」
と気遣いやねぎらいの言葉をかけられると、とても嬉しくなりますね。あなたが優しい言葉をかければ、相手も喜ばれるでしょう。
その際のポイントは、目に見える結果よりも、目に見えない相手の「苦労」「努力」「工夫」がどこにあるのか探すことです。
例えば、おいしいレストランでごちそうになったのなら、
「素敵なお店ですね。どうやって探してくださったんですか。ありがとうございます」
と、数ある中でもそのお店を選ばれた相手の「苦労」に気づくと、とても喜ばれます。
身施(しんせ)
体を使って、ボランティア・奉仕活動をすることです。
奉仕活動というと、「有休をとって、被災者のために働くこと」のように思われるかもしれませんが、それだけが奉仕活動ではありません。
オフィスのたまったゴミを捨てたり、なくなった消耗品を補充したり、年配の方が歩かれていたら、重い荷物を持つのを手伝うのも身施であり、素晴らしい善行です。
心施(しんせ)
「ありがとう」
「すみません」
「うれしいです」
と、心から感謝の心を述べることです。
最近流行りのアドラー心理学では、相手を勇気づけるのに最も簡単で効果的な方法が「感謝の言葉を述べること」だと言われます。
私たちはついついしてもらっていることを当たり前に思い、感謝を忘れてしまいがちですが、それは本当に残念なことですね。
ひと言、「ありがとう」があるかないかで、人間関係は大きく変わってきます。「ありがとう」があればお互いが気持ちよく過ごせますし、「ありがとう」がなければギスギスした関係になってしまうでしょう。
感謝を伝える機会を積極的に探していきたいですね。
床座施(しょうざせ)
場所や席、立場をゆずる親切をいいます。
毎日のことでいえば、
- 通勤電車の座席の取り合い
- テレビのチャンネルの争奪戦
- カラオケのマイクの奪い合い
- 宴会で、どちらが上座にすわるのかのいがみ合い
- 車の割り込み運転は許さないぞと、車間距離を詰める
などなど、こんな時に心がけひとつで、「お先にどうぞ」と気持ちよくゆずってあげると、清々しい気持ちで過ごすことができます。
房舎施(ぼうしゃせ)
家に訪ねに来た人に、一晩の宿と、食事をもてなすことです。
今ではないことですが、仏教が説かれたインドでは、昔、布教に歩く僧侶がいたので、その僧侶が夜になって家を訪ねてくることがあったそうです。
そのときに快く一晩の宿と、食事をもてなす、それが房舎施ですね。
これらが、お金がなくても、物がなくても、心がけさえあれば周りの人たちに喜んでもらうことができる善い行いだから、ぜひやりましょうと勧められています。
日々の生活で実行し、周りの人たちを大切にしていけば、人間関係もスムーズになり、必ず自分も大事にされるようになっていきます。
常にできる「布施」は無いだろうかとアンテナを張って、実行していきたいですね。