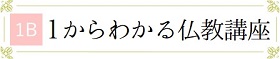「7つの習慣とお釈迦さまの教え」講座 -まず理解に徹し、そして理解される- ②

前回は「7つの習慣」の第5番目の習慣である「まず理解に徹し、そして理解される」の内容を一部、ご紹介しました。
相手のことを正しく理解するには、相手の話を聞くより他にありません。
その聞き方のレベルに5段階あると7つの習慣に書かれています。
それは以下のように教えられています。
- 無視して、聞こうとしない
- 聞くふりをする
- 選択的に聞く
- 注意して聞く
- 共感による傾聴
レベル5の「共感による傾聴」以外、相手の話を聞いているようで、実は自分の話をしてしまっている、ということを前回、お話ししました。
相手の話を聞いているようで自分の話をしていることを「自叙伝的な反応」と教えられています。
相手の話を盗んではいけない
わかりやすい自叙伝的な反応は「相手の話を盗む」行為です。
たとえば
「実は先週、ディズニーランドに行ってきてさ…」
「あ、実は私も行ってきたの! こことここを回って、それで…」
というように、相手の話題を奪って自分の話をすることが「相手の話を盗む」行為ですね。相手の話を聞くのが目的なのに、話を盗んで自分が話をしては本末転倒です。
私たちは相手の話を聞くより、自分の話を聞いてもらいたい気持ちいっぱいなので、気をつけないとこれさえやってしまいますね。
4つの自叙伝的な反応とは
話を盗むのはあからさまな自叙伝的反応ですが、ここまではいかなくとも実は自叙伝的な反応といえる反応が4つあることを7つの習慣で教えられています。
それは以下の4つです。
- 評価する・・・同意するか反対するか
- 探る・・・・・・・自分の視点から質問する
- 助言する・・・自分の経験から助言する
- 解釈する・・・自分の動機や行動を基にして、 相手の動機や行動を説明する
自分の視点から質問をしたり助言をしたり、解釈をするのも自分の考えを相手に押し付けようとする行為なので、自叙伝的な反応にあたります。
また相手の言ったことに反対するだけなく、同意することも自叙伝的な反応といわれます。相手の事情をよく知った上で、相手の考えを尊重するべく同意をしているのならいいのですが、相手の状況を知ろうともせず、自分の立場にたっての同意は自叙伝的な反応となってしまうのです。
肝心は、相手の行ってきたことに対し、頭ごなしに反対をしたり、いきなり同意をしたり、勝手な解釈をせずに、まず相手の言葉を受け止めることです。
「ああ、あなたは○○だと思うんだね」
こう反応するのが相手を理解する聞き方のはじまりなのですね。
相手を理解する聞き方にも4段階あると学びました。それについては機会があればご紹介したいと思います。
講座に参加された方の感想
分かり合えないからこそ、よく聞くことが大事
なかなか人の話を注意して聞くことは難しいですが、分かり合えないからこそよく聞くことが大事だとわかり、なるほどと思いました。
ありがとうございました。
(20代・男性)
相手を理解するとともに、自分の心も届ける
相手を理解するだけなく、自分の心を相手に届けることも大切、というのが心に響きました。
相手を理解しようとすることにだけ注力すると無理がきていびつな結果になるので、両方バランスよくできるようになりたいです。
(女性)
無意識に聞くふりをしたり、選択的に聞いていた
人の話を聞くとき、無意識に聞くふりをしたり、選択的に聞いていたように思う。
そして自叙伝的な反応をしていた。
これからは意識して、理解する聞き方をしたいと思った。
(男性)